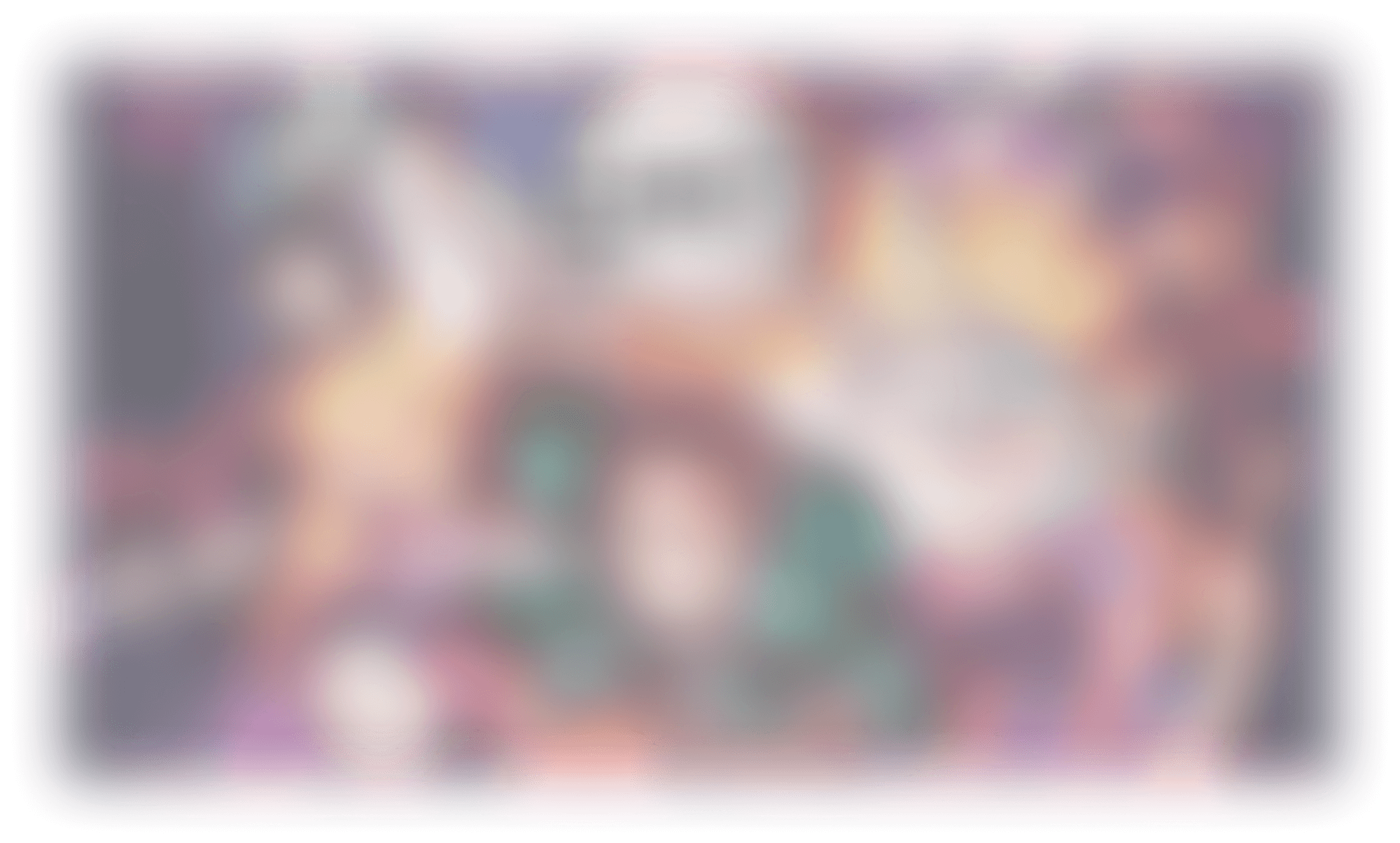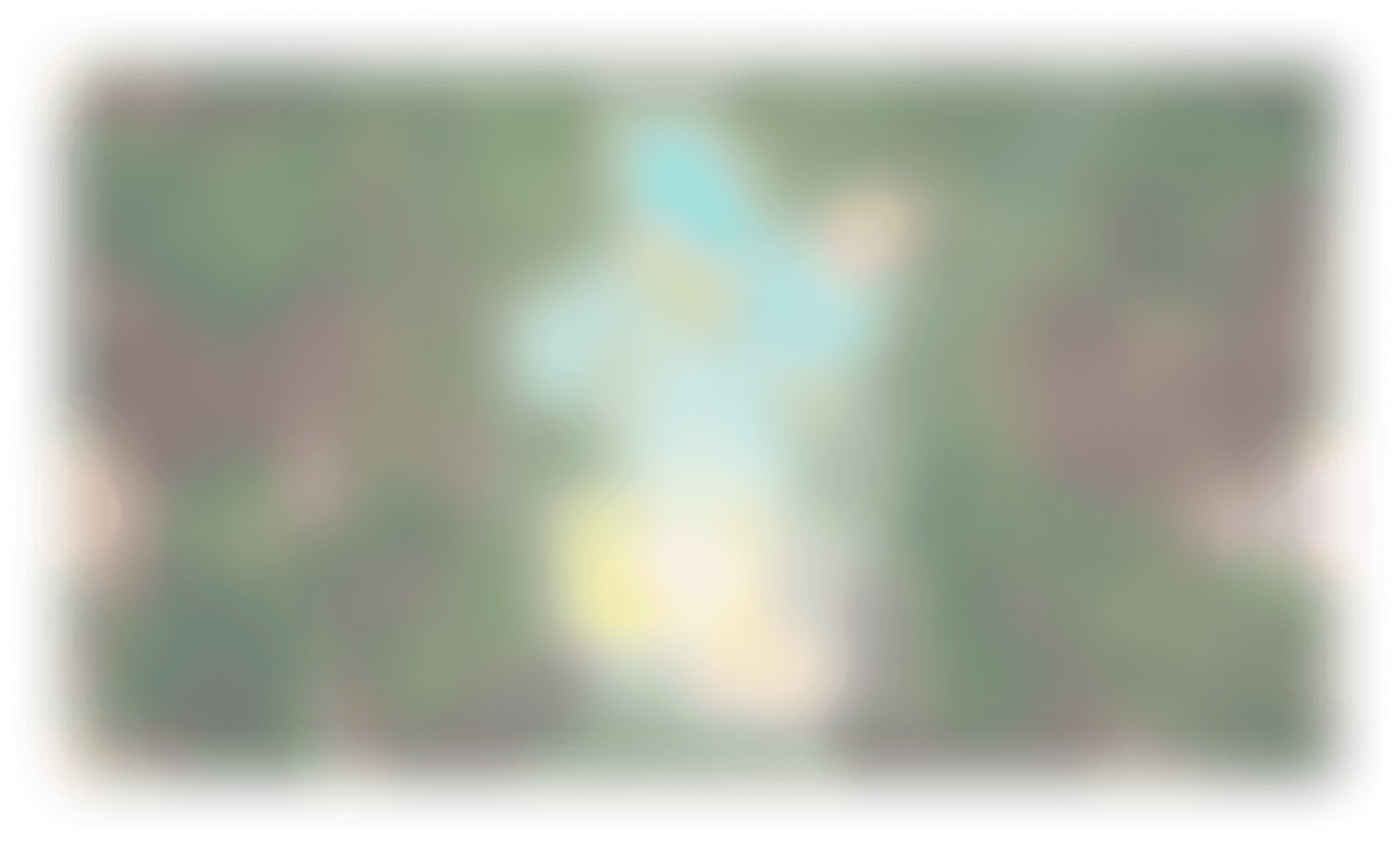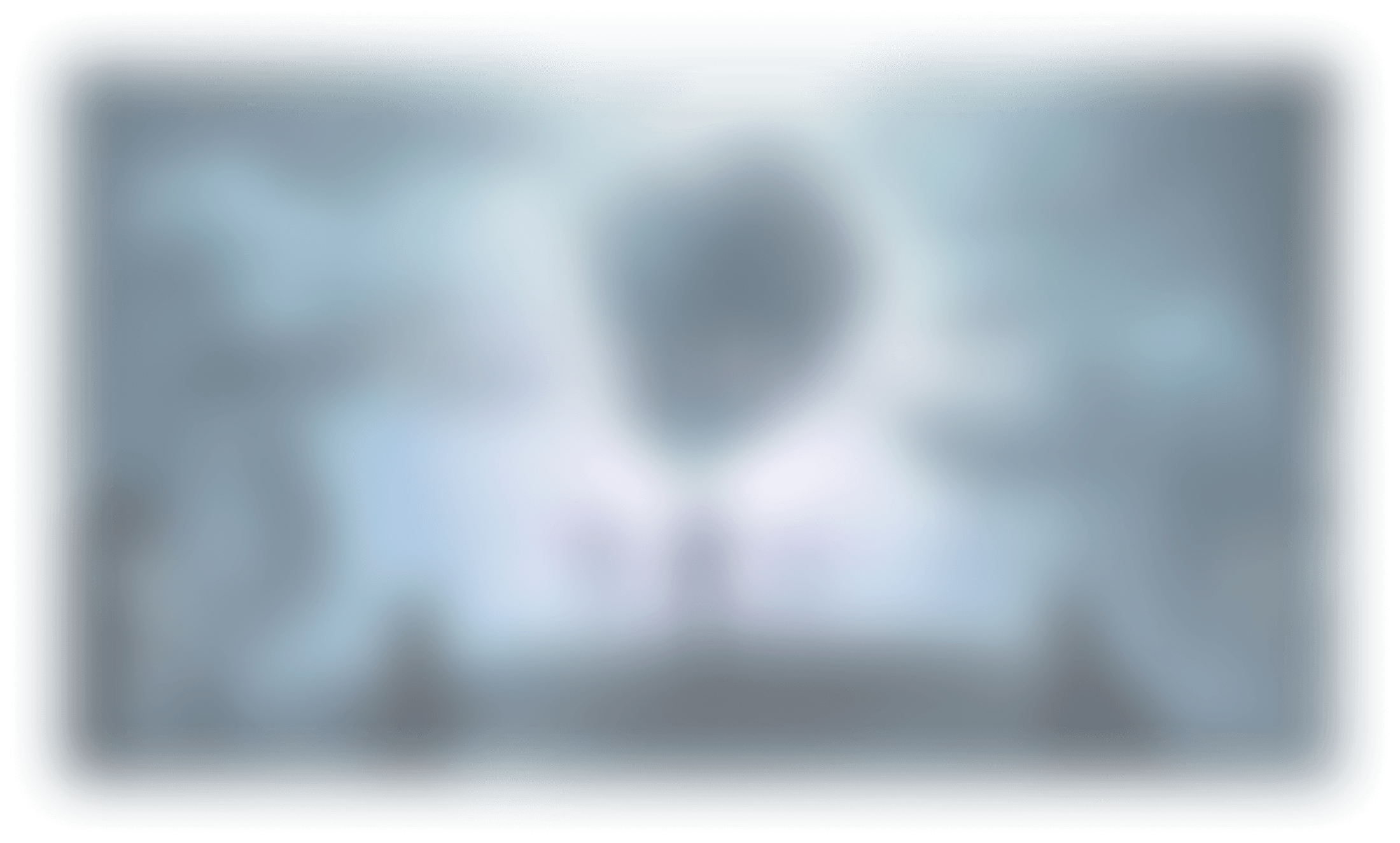トップランナーとの差を埋めるために、豊富なノウハウを持つパートナーを求めた
──まず、会社紹介ムービーなどのデジタルコンテンツ制作をLampTokyoに発注した経緯からお聞かせください。

三国:そもそも、私たちマーケティング戦略統括部に与えられたミッションはマーケティングオートメーション(以下、MA)を実現し、その運用を確立することです。MAの目的はデジタルマーケティングによって、顧客を獲得すること。さまざまなチャネルを活用して見込み顧客にアプローチし、ホームページなどに呼び込むわけですが、呼び込んだところで会社や私たちが販売している建機の魅力が伝わるコンテンツがなければ受注には繋がりません。
しかし、2019年ごろまではそういったコンテンツが充実しているとは言えない状態でした。これではいくら見込み顧客に認知され、興味を持ってもらったとしても、比較検討のフェーズには進んでもらえません。そこで、デジタルコンテンツを充実させなければと考えたのですが、いかんせん社内にはノウハウがありませんでした。これでは他社に遅れを取る一方だと危機感を持ち、コンテンツ制作のパートナーを探し始めました。
──デジタルマーケティングに力を入れなければならないと考えたのはなぜでしょうか。
深川:業界全体の流れですね。以前から徐々にデジタルシフトの波が建設機械業界にも起きていたのですが、流れが一気に加速したのは新型コロナウイルス感染症の影響です。急速にトップ企業がデジタル化を進める中、私たちは、対面営業力に注力してきたので、デジタルマーケティングに力を急速に対応・融合させなければならないと危機感を感じました。
三国:当然、ノウハウも無いですし、それ以前に会社全体としてデジタルマーケティングの優先度がそこまで高くなかった。ホームページ上のコンテンツの充実度が低いことに対する共通認識はあったものの、そこを強化したところで業績に結びつくのか分からず、後回しになってしまっていたわけです。
──そういった背景から、デジタルコンテンツ制作に強みを持つパートナー探しが始まったんですね。
深川:コンペというほど大層なものではないのですが、LampTokyoだけではなく、さまざまな会社に声を掛け、各社に簡単な映像を制作する課題に取り組んでもらいました。その結果、LampTokyoのアウトプットが群を抜いていた。それだけではなく、企画プロセスにおいても他社との違いを感じて、2020年の4月ごろ、パートナーとして契約を結んでもらいました。
会社のビジョン、想い、カルチャーありきのコンテンツ制作
──LampTokyoと他社との違いとはどのようなものだったのでしょう?

深川:私たちの想いやビジョンを大切にしてくれる点です。まず的場さんは、ただ「どんな映像を作りたいか」と聞くのではなく、映像を作る意味、つまり「会社として現在だけでなく将来的に何を目指すために映像にするか」を丁寧にヒアリングしてくれました。そこがとても印象的でしたし、今思えばそこがLampTokyoらしいなと。
──その際はどんなお話を聞いたのですか?
的場:深川さんが「エンジニア志望の学生たちが、憧れるような業界にしたい」と語ってくれたのをよく覚えています。現状では、大学を出たエンジニアたちにとっての憧れの業界と言えば、ITや自動車業界でしょう。確かに先進的なイメージがありますし、とても魅力な業界です。
しかし建設機械業界も自動車業界に負けない魅力があるはずなのに、それが伝わっていないのが悔しいと深川さんは真剣に仰っていた。わたし個人としても、子供の頃から建設機械は純粋にかっこいいと思っていますし、街や社会を創る建設機械は、エンジニアたちにとってもやりがいのある業界だと感じていました。だから、深川さんの想いに共感しましたし、そのお手伝いがしたいと思ったんです。
──他にはどんなことをヒアリングしたのでしょう?
的場:会社のカルチャーや社風ですね。与えられた課題であり、最初に手掛けさせてもらったのは日立建機日本の会社紹介ムービーだったのですが、どんなにおしゃれでかっこいい映像を作ったとしても、その映像が正しくその会社を映し出すものでなければ意味がありません。それは会社紹介ムービーだけではなく、全てのコンテンツに言えることだと思います。だから、まずはその会社にどんな特徴があるのかを深く知りたかった。
そうして社風やカルチャーをヒアリングした結果、日立建機日本さんは「ヒト」に強みがある会社だということが分かった。これまでヒトの良さ、言い換えれば営業力で勝って来た会社なんです。実際、日立建機日本の方々と話してみると、ヒトが最大の強みであることがすぐに理解できました。本当に素直で実直な、気持ちの良い人が多い。だから、会社紹介ムービーを作る際は、働く人たちの想いにフォーカスした内容にしようと提案しました。
深川:的場さんの言う通り、私たちの最大の強みは営業力です。そのベースになっているのは、ヒトの良さ。しかし、それは裏を返すと弱点でもある。的場さんが「素直で実直」と言いましたが、本当にその通りの人が多い。「良く見せよう」とか「うまく表現しよう」という思考があまり無く、それがマーケティングやブランディングの遅れに繋がっていたように感じます。
──そういった御社のカルチャーをも汲み取ってコンテンツを制作しようとする点に魅力を感じた。
深川:それに、映像だけではなく、さまざまなコンテンツをワンストップで制作していただけることも大きかった。
三国:発注した当初から「あれもできる?これもできる?」とその後の展開を考えて、いろいろと相談していたんですよね。SNSの運用などについても明確なアイデアがあるように感じましたし、幅広く丁寧に対応してもらえる印象を受けました。かっこいい映像を作ったとしても、その映像が正しくその会社を映し出すものでなければ意味がありません。それは会社紹介ムービーだけではなく、全てのコンテンツに言えることだと思います。だから、まずはその会社にどんな特徴があるのかを深く知りたかった。
会社としての販促だけではなく 「業界のブランディング」までを視野に入れた提案をする
──かなり最初の段階から、広範な業務も任せることを検討していたんですね。
深川:それだけ、最初に制作していただいた会社紹介ムービーの企画力とクオリティが高かった。これならいろいろとお任せできるなと思いましたし、今思えばかなり金額的にもスケジュール的にもかなり無茶をさせてしまっていたのですが、それでも嫌な顔一つ見せず、柔軟に対応してくれましたしね。
──幅広い業務を任せられるにあたり、的場さんとしてはいかに戦略を立てていったのでしょうか。

的場:三国さんが言っていたように、すでに「コンテンツをMAに活かし、顧客へのアプローチを強める」という大枠の戦略がありました。その戦略をいかに遂行するかについてですが、僕としてもBtoBのマーケティングの経験は豊富ではなく、一緒に学んでいったような形です。
toCであれば、『Instagram』や『YouTube』『Twitter』を活用するアイデアはすぐに思いつきますが、toB領域ではそういったアプローチの効果が見えにくい。実際に建設機械を利用するお客様たちはどのような映像、コンテンツであれば「いいね」と思ってくれるのかを一番最初に考えました。
ただ、日立建機日本さんがコンテンツを作る意味は、売上向上だけではないことは先に言った通りです。「建設機械業界を優秀なエンジニアにとっての憧れの舞台にする」という目標までを考えると、現在進行系で機械を利用している建設業界だけにアプローチするだけでは不十分。そこで、toCに対するブランディングに繋がる『Instagram』などの活用も含めて提案させてもらいました。
──既存顧客、潜在顧客に対する販促はもちろんのこと、将来の働き手に対するブランディングも視野に入れた提案をしたわけですね。
的場:たとえば、建設機械が好きな若者が日立建機日本さんの『Instagram』を見て、「やっぱりかっこいいな」あるいは「やりがいのありそうな業界だな」と思ってもらい、この業界を志してもらうことが一つの目標です。
メンバー全員が「何かあればLampTokyoに聞いてみよう」と思える関係性
──ただ、LampTokyoはそこまで規模が大きな会社ではないですよね。日立建機日本という大企業の、様々なコンテンツ制作を担うことに不安はありませんでしたか?
的場:それはもう大きなプレッシャーを感じましたよ(笑)。ただ、同時に日立建機日本さんも不安を感じていたのではないかと思っていて。というのも、私もかつては「発注する側」にいたので、マーケティング担当者が背負う責任はよく分かっているつもりです。規模の小さな会社にお願いするときって、多少なりとも不安はある。もし上手くいかなかったとき、会社から責任を問われるのは発注した担当者になるわけですから。だからこそ、我々も同じ土俵に立ってパートナーとしてそのプレッシャーを感じるべきです。そう考えると、三国さんと深川さんが短期間のうちに大きな信頼を寄せてくれたのは本当にありがたかった。

深川:誤解が生じないように言っておきますが、私たちはどんなパートナーさんにもすぐに全幅の信頼を置くわけではありません。むしろ、そのジャッジは厳しい方だと思っていますよ(笑)。
──現在はすでにいろいろなプロジェクトが動いていると思うのですが、どのように連携を取りながら業務を進めているのでしょう?
深川:弊社内の体制を説明しておくと、デジタルマーケティングに携わっているのは総勢14名。うち、8名が専任のメンバーです。どのように施策を考えているかというと、かなり発散的にディスカッションをして、その中で生まれたアイデアを実行するような形ですね。同業他社に比べても、かなりクリエイティブな組織になっているかなと思います。しかし、ラフアイデアが浮かんでも、いかんせん企画に仕上げて実行するためのノウハウが無い。そこで、LampTokyoの出番です(笑)。
的場:「こんなことがやりたいと思っているんですが」といった相談から、「すでに動いているプロジェクトがスタックしちゃって……」といったものまで、様々な内容の連絡を毎日のようにいただいています。
三国:的場さんと日々コミュニケーションを取るのは、私たち2人だけではありません。弊部メンバーたちが「LampTokyoに聞きたい」と言うことがあれば、遠慮せず連絡することを勧めていますし、入社2年目のメンバーから管理職まで、気軽にコミュニケーションをさせることで共にプロジェクトを進めています。
それに、LampTokyoのメンバーのみなさんとも、頻繁に密にやり取りをさせてもらっていますよ。的場さんのみならず、組織と組織として良いパートナーシップが築けている。
社内にデジタルコンテンツの力を示すことが重要
──かなり順調にさまざまなプロジェクトが推進されている印象を受けるのですが、課題は無いのでしょうか。

三国:強いて挙げるとすれば「私たちの取り組みの成果を、社内にしっかりと示していくこと」でしょうか。デジタルマーケティング、とりわけコンテンツ制作は簡単に大きな成果に繋がるわけではありません。ただ、やはりデジタル施策をうまく活用していかなければ、大きな成長は望めませんし、時代に取り残されてしまう。だからこそ、現在私たちが進めているプロジェクトが「どれだけ会社に貢献しているのか」を明確にし、その力を認識してもらう必要がある。
MAの成果とは数字、つまり「どれだけ売上に貢献したか」が問われますよね。すでに分かりやすい効果は現れているんです。2020年4月にリニューアルした会社ホームページのPV数は、前年同時期比で2倍ほどになっている。やはり、顧客が見たいと思えるコンテンツを用意すれば、しっかりと見てもらえるわけです。
しかし、そのPV数がどれほど「会社の売上に貢献したか」を正確には判断できない。会社紹介ムービーや『Instagram』活用はブランディングに紐づく施策なので、成果はなおのこと分かりづらい。今後はさまざまなデジタルコンテンツが、いかに会社に貢献しているのかを示すための仕組み作りに力を入れていきたいですし、LampTokyoにも相談しているところです。
的場:ブランディングに関する「誰もが納得する結果」は、結局は調査データでしか得ることができません。しかししっかりとした戦略をもとに様々な施策を継続することで、調査データ以外の尺度で必ず成果を感じることができると思っています。
今はまだ「砂上の楼閣」。 デジタルマーケティングを会社のカルチャーとして根付かせるために
──約1年半ほどプロジェクトを推進してきていますが、現段階での手応えを深川さんはどのように感じていますか?
深川:大きな手応えを感じています。手前味噌になってしまいますが、この1年半、とてつもないスピードで膨大な業務をLampTokyoと一緒に進めてきました。映像20本以上に加えて、300を超えるWebページを制作しました。
その効果は確かに現れている。知り合いの同業他社の方々と会うと「日立建機日本さん、最近どうしたの?デジタルマーケティングすごいじゃん」と言われることが多いんです。先程三国が言ったように、ブランディング施策は利益に直結するものではなく、効果も分かりづらいですが、周囲からの認識が変わりつつあることを肌で感じています。
──これからLampTokyoと共に、どんなことにチャレンジしていこうと考えていますか?
深川:引き続き、マーケティングやブランディングに寄与する映像制作は続けていきます。その上で、より一層ホームページなどに掲載するデジタルコンテンツを強化していきたいですね。映像ではないコンテンツで、顧客に弊社の商品に興味を持ってもらったり、購買意欲を高めたりする方法を模索したいと考えています。
三国:オフライン施策もご一緒していきたいですね。私たちは定期的に展示会などに出展しているのですが、そういったリアルな場でのプロモーションにも力を貸してほしいと思っています。もちろん、弊社の体制としてもLampTokyoとしても「すぐに」とは行かないかもしれませんが、オンラインだけではなく、オフライン施策もご一緒できれば心強いですね。
──マーケティングやブランディングに関する取り組みを始めたころから比べると、かなり前に進んだような印象を受けます。
三国:そうですね。ただ、まだまだ始まったばかりですし、これまで積み上げてきたものは「砂上の楼閣」と言ってもいい。つまり、何かあれば簡単にゼロに戻ってしまうような状態だと認識しています。もし部署のメンバーが変わったとしても、デジタルマーケティングを日立建機日本の確固たる武器として使えるようにしなければなりません。
深川:そういう意味でも、今年は勝負の年。大きな成果を挙げて、社内外に「日立建機日本はデジタルマーケティングに強みを持つ会社だ」と認識してもらうための土台を構築したい。そのために、LampTokyoの力は欠かせません。これからも共に大きな目標に向かってチャレンジしていきたいですね。

【取材・文】鷲尾諒太郎 【撮影】小川拓郎
【協力】日立建機日本株式会社 https://japan.hitachi-kenki.co.jp/